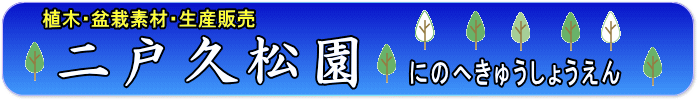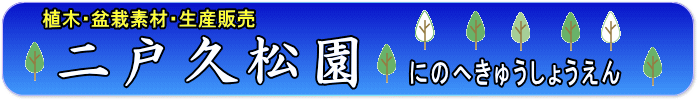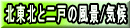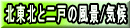 |
1.お知らせ欄 2.新着情報価格案内 剪定(強剪定)の紹介 3.クリスマスツリー案内
4.外部リンク 5.内部リンク 6.画像情報 7.観察情報 |
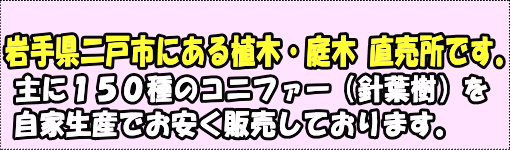
|

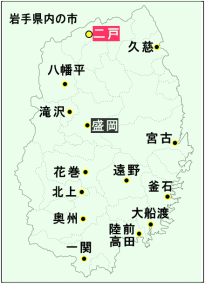 |
1.お知らせ欄
2025/01/25当園名【二戸久松園】を冠した悪質と思われるサイトが数多く確認されています。 ご注意下さい。 詳細はこちら
2025/01/25 送料が大幅に値上がりいたしました。送料はこちらの運賃表で確認できます。問い合わせ頂きすと写真を送り、送料込みの総額をお知らせいたします。そのうえで購入を 「する」 「しない」 を検討していだだきます。
2025/01/25 サムネイル(縮小画像)で編集しております。サムネイルの説明 リンク説明 リンク説明
画像上をクリックすると拡大します。拡大画像の右側クリックで次の画像に進み、左側クリックで戻ります。画像が下方にずれて表示されることがありますので画像が出ない場合は画面を下方に移動してみてください。
2025/03/6
当園オリジナル(ニオイヒバ品種) の商品名はカシオペアゴールドです。 ※カシオペアゴールドは北岩手(二戸市・一戸町・軽米町・九戸村・旧浄法寺町)をカシオペア連邦の愛称で呼んでいいることから商品名としました。。 の商品名はカシオペアゴールドです。 ※カシオペアゴールドは北岩手(二戸市・一戸町・軽米町・九戸村・旧浄法寺町)をカシオペア連邦の愛称で呼んでいいることから商品名としました。。
2025/03/24
まだ残雪
 がありますが2025年の営業を開始いたしまいた。お問い合わせはこちらを参照 がありますが2025年の営業を開始いたしまいた。お問い合わせはこちらを参照
|
2.新着情報案内剪定(強剪定)の紹介
新着情報  |
| 赤松系 |
赤松 | 多行松 | 八房赤松 | 枝垂れ赤松/天目松(テンモクショウ) |
| 黒松系 |
黒松 | 寸梢黒松 | 岩石性黒松 | 錦松 | 蛇の目黒松 |
| 五葉松系 |
谷間の雪 | 八房五葉松 | 北五葉松 | ハイ松 | 吾妻五葉松 | 短葉種五葉松(当園オリジナル) |
ヒマラヤ五葉松 | ストローブ松 | 五葉松(ヒメコマツ) | 玉華仙五葉松 | 宮島黄金五葉松 |
朝鮮五葉松 | 蛇の目五葉松 | 荒皮錦五葉松
|
| その他の松 |
バンクス松 | モンタナ松 | |
| 植栽例 |
フィリフレアオーレア | エメラルドグリーン | ヨーロッパゴールド | ブルーパシフィック | 一才イチイ |
紀州シンパク | 五葉松 | 黒松(岩石性) | 当園オリジナル品種(商品名 カシオペアゴールド |
ヒムロスギ | 八房赤松 | アスナロ | コメツガ | エゾマツ | コニカ | タマイブキ |
|
サワラ / ヒノキ系 |
イトヒバ/黄金イトヒバ | ヒムロ杉 | 石化ヒノキ | サワラ | スイリュウヒバ |
チャボヒバ/黄金チャボヒバ | 黄金クジャクヒバ | |
| 落葉樹/その他 |
ムラサキシキブ | シロシキブ | イチョウ | モミジ | サルスベリ | カルーナ |
コニファー(Conifer)
|
ブルーカーペット | ブルーパシフィック | ビャクシンピラミダリス | ブルースター | ラインゴールド
レパンダ | プンゲンスホプシー/プンゲンストウヒ/コロラドトウヒ | カナダトウヒ/コニカ | ゴールデンピラー |
ヘッツィー | ブルーチップ | デグルーツスパイヤー | フィリフェラオーレア |
ヨーロッパゴールド | エメラルドグリー ン| グリーンコーン | プンゲンストウ | ヒニオイヒバピラミダリス |
ニオイヒバピラミダリス | センパオーレア | サンキスト | オールドゴールド |
|
| ツガ(栂)系 |
コメツガ(米栂) | カナダツガ | シダレコメツガ(枝垂米栂) |
| イチイ系 |
イチイ(オンコ) | キャラボク | キンキャラ | 一才イチイ |
| イブキ(ビャクシン)系 |
ハイビャクシン(浜ハイビャクシン) | タマイブキ | 紀州シンパク(真柏) | 糸魚川シンパク(真柏) | 八房ソナレ |
| トドマツ・モミ系 |
トドマツ | ウラジロモミ | コーカサスモミ | バルサムモミ | コロラドモミ | シラビソ |
| クロベ属 |
当園オリジナル品種(商品名 カシオペアゴールド) | ワビャクダン | クロベ |
| スギ / トウヒ系 |
ドイツトウヒ(欧州トウヒ) | セッカンスギ(雪冠杉) | エンコウスギ(猿猴杉) | チャボスギ(矮鶏杉) |
コロラドトウヒ | ビロードスギ | |
| エゾマツ/トショウ系 |
アカエゾマツ | ネズ(トショウ ネズミサシ) | エゾマツ(クロエゾマツ) | 八房エゾマツ |
ヒマラヤスギ属
|
ヒマラヤシーダ | レバノンシーダ |
コウヤマキ属
ウスリーヒバ属
イヌガヤ属 |
コウヤマキ(高野槙) | ウスリーヒバ | チョウセンマキ |
|
|
|
3.クリスマスツリー案内 |
 クリスマスツリー木 クリスマスツリー木
Christmas Tree
本物のクリスマスツリー生木(伐採樹)販売 ・通販
各種イベントの引き立てに
ウラジロモミ(モミの木) | ドイツトウヒ | ニオイヒバピラミダリス | エメラルドグリーン |
グリーンコーン | ヨーロッパゴールド | フィリフレアオーレア | コウヤマキ
クリスマスツリー鉢仕立て2例記載 |

ドイツトウヒ |

ウラジロモミ |

コウヤマキ2024/10 |

コウヤマキ2024/10 |
|
|
4.外部リンク
|
|
|
|
|
|

アオモリトドマツ
|
アオモリトドマツ |

アオモリトドマツ |

コメツガ
|
|
2020/03 鉢で育てていたアオモリトドマツ(オオシラビソ)の実生苗を成長を早める為、地植えいたしました。
直根や伸びている根は細根を作る為、この段階で途中から切除しました。 当地方は冬季マイナス10℃以下になることもあり地面が凍ってしまいます。3月中旬頃になると地面が溶けたり凍ったりして根が浮き上がります。冬が近づいたら稲わらで根部を覆い対処します。またネズミ、モグラが掘り起こして根が浮き上がることもあります。スギ葉、トショウ葉を埋めて置くと近づきません。葉が尖っているので触ると痛いのでしょう。
成長過程で枯れる割合が多く、なかなか提供出来ない品種です。高山に生育する樹木で暑さには弱いですが、苗は木陰に植えて育てるので暑さで枯れることは少ないでしょう。苗木は日照がほとんど無くても育ちます。枯れる原因は冬の寒風による乾燥かと思っています。当地方降雪量が少ない年が多くなり雪が積もって乾燥を防ぐことが出来ない状態です。多雪環境に適している木なので、生育に適さない環境のもとでは枯れることも多くあるのかと思います。幼木は極めて成長の遅い木です。樹高50㎝にもなれば樹勢も付き成長も早くなります。それまでの管理が大事になります。
コメツガも極めて成長の遅い木です。画像は実生3年目になります。種は1ミリにも満たない大きさで発芽率は極めて低く短期間での生産は不可能です。
|
|
|
|
|
野すみれ/山すみれ ミヤマリンドウ 当園圃場に野すみれがあちこちに咲いています。ただ土を掘り起こしたり、除草の際一緒に取ってしまうので大分数が減ってきました。 通常花を咲かせる時期は3~5月頃のようですが、当園圃場では早春から晩秋まで長い間代わる代わる花をつけます。春雪が融けるともう花が咲いています。遅いものは12月になって雪が降っても咲いているものもあります。
ミヤマリンドウも圃場に自然に咲きます。こちらも土の掘り起こしや除草で数が減ってきました。10月下旬頃には綺麗な花を咲かせます。天候次第では開花しないでつぼみで終わるものもあります。
農作業で疲れた時など華憐に咲いている花をみればひと時の安らぎを感じます。 |
|
|
( ) は当地方の呼び名です
|
|
カワラヒワ(キロ)がエメラルドグリーンによく巣を作ります。巣立ち直後のまだよく飛べない時期カラスの餌食になることもあります。自然の摂理とはいえ助けてあげたいと思うことがあります。 当園樹木に野鳥が巣を作る例はたくさんあります。ただ野猫/野良猫、ヘビ、カラス、イタチ等の外敵も多く順調にヒナが巣立つことができないこともあります。当園樹木で育って巣立ちを見かけたものはホウジロ(ストド)、モズ、鳥アカハラ、カワラヒワ(キロ)がいます。
渡りの途中、当園圃場に多くの野鳥が立ち寄ります。冬渡って来たツグミ、シメ(マメッチョ)、マヒワ(シュワ)、ベニマシコ(マスコ)は北に帰る途中よく立ち寄ります。遅いものは5月中旬頃までみかけることがあます。変わって4月下旬には夏鳥のオオルリ、クロツグミ(コッケ)キビタキ、ノビタキが立ち寄ることがあります。長くても三日ほど居て山麓に移動します。
10月中旬頃には北からやって来るジョウビタキをよくみかけます。数日後にはより南に向かっていきます。4月頃には今度は北へ帰る途中立ち寄ります。 |
|
|
|
|
イチイの実を運ぶヤマガラ。 イチイから取った実の果肉は捨て種だけどこかに運んでいます。貯めて餌の乏しい冬食べるのでしょう。食べ残した種がいろんな場所で芽を出して成長することがあります。ヒヨドリ(ピーピー)も食べますが、ヤマガラは種を両足でつかみ嘴で殻を割って中身を食べますが、ヒヨドリ(ピーピー)は果肉を捨て種を丸呑みします。熟して地面に落ちた実は野ネズミが食べます。イチイの種には毒が含まれています。人間が食べると危険です。果肉は食べられますが種を噛み潰したり飲み込むは絶対避けましょう。
ヤマガラなどカラ類は冬一緒に行動し、餌を求めて木々を飛び回ります。よく当園圃場にもやって来ます。先頭はいつもシジュウカラで、その後にはヒガラ、エナガ、コガラ、ヤマガラ、キクイタダキが混在し最後尾はいつもコゲラです。
イチイの他、ナナカマド、南天、紫式部などもの実も鳥が食べますが、好んで食べることはありません。大雪などで餌が乏しくなった時などしか食べません。大雪の日、アトリ(アワ)がナナカマドの実を大群で来て食べていることを見たことがあります。果肉は捨て種だけを飲み込むので雪の上には果肉がいっぱい落ちて真っ赤になっていました。 |
|
|
|
鳥はエゴマが大好き カラスが刈り取り後のエゴマ畑で、こぼれたエゴマをあさっています。他にキジバト(ヤマバト,デデポッポ)、ホオジロ(ストド)、スズメが集まってきました。刈り取った後はハウスで乾燥して脱穀するので、こぼれた実以外は食べられることがないので安心です。
穀類を食べる野鳥はたくさんいますがエゴマが一番好まれます。杉の種を食べるマヒワや松、トウヒ類の種を食べるイスカはエゴマだけても育ちます。マヒワ(シュワ)はヒエも食べますがヒエだけ与えると死んでしまいます。穀類を食べる鳥は多いですがヒエやアワとエゴマでは、エゴマの方を好んで食べます。
川魚もエゴマが大好き ハヤ(シラヘ)、アブラハヤ(ノマヘ)もエゴマを好んで食べます。子供の頃ジュネ(エゴマ)釣りをしたことを覚えています。口に入れ噛み潰して淀みに吹くと匂いで魚が集まって来ます。エゴマ実に似た疑似餌が付いた釣り針をたらすとよく食いつきました。
エゴマ生産販売は2020年で終了いたしました。 |
|
|
|
剪定はハチに注意 当地方の剪定依頼はお盆前に集中します。ハチが活発に活動する時期になります。
よく木の枝に巣を作るコアシナガバチがいます。攻撃性は弱く、巣を揺するか触らないかぎり攻撃されません。当園の植木にも沢山作っており、剪定中よく見つけ駆除しています。
キイロスズメバチ(カメバチ)もよく木に巣を作ります。攻撃性が強く、剪定時攻撃される前に気づいて駆除することが重要です。長い棒などで木を揺すったり、叩いたりして確認します。ハチが飛び回ったら巣があると思ってください。よく土中に巣を作るクロスズメバチ(シガリ)も怖いハチです。巣を踏みつけるものなら集中攻撃を受けます。剪定には上方にも下方にも十分注意が必要です。
|
|
|
|
6月剪定中,蜂の巣を見つけ駆除しました。女王蜂が一匹で巣を作り卵を産み働きバチを増やしていきます。女王蜂一匹の時は巣からほとんど離れづ、攻撃もほとんどしてこないので剪定バサミで捕まえて駆除しています。巣近くの枝を揺するとブンブン飛び回るので近辺を探すと必ずあります。しばらく静かにしていれば巣に戻ってきます。その時捕獲します。巣だけ取り除いても女王蜂が生きているかぎり、また別の場所に巣を作り始めます。働きバチが誕生するとスズメバチ(カメバチ)の場合は近づくことも危険になります。 9月になるとキイロスズメバチの巣は大きさは30㎝以上になるものもあります。こうなると簡単に駆除できないので女王蜂が一匹の時は剪定バサミで捕まえて駆除するようにしています。
11月気温が低い朝は、ハチの動きが鈍くなり飛ぶことが出来ません。このとき簡単に駆除することが出来ます。次の女王バチは、木の隙間などで冬越しします。積んでいる薪の中からみつけることもよくあります。 |
|
|
|
6月下旬の蜂の巣 蜂はいろんな場所に巣を作ります。なかでも軒下がもっとも多いと思われます。6月下旬には働きバチが誕生しています。こうなると殺虫剤スプレーでの駆除になります。
アシナガバチは防護服なしで駆除していますが、スズメバチ(カメバチ)は防護服を装着しています。麦わら帽子(体験から麦わら帽子を被っていると攻撃されにくいと感じています)に網を被り、雨合羽、ゴム手袋、長靴を身に着け、殺虫剤2本と長い棒を用意します。後は殺虫剤を駆けながら巣を落とします。落とした巣は踏みつぶします。そのままにして置くと戻って来て幼虫を育てる可能性があります。 |
|
|
|